 |
|
▲安孫子義彦氏
|
昔の設備は当然のことながら天井裏配管でした。古い建物を見ますとほとんど天井裏に排水配管が入っていて、必要なところでスラブ貫通して設備機器につながっています[fig.1-01]。それが、あることをきっかけに床上で全部処理しようという考えになってきました。それが昭和37年の区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)で、上下の区分所有・管理を含めて別の区分にしようということになってきたために、設備もそのあおりを受けざるを得なかったわけです。床下で処理するのと床上で処理するのとでは、どのような差があるのかというと、[fig.1-01]の表で○が付いているのはだいたいよいということです。いわゆる区分所有が明確になるとか、維持管理が床上からできる、防火区画の貫通処理がなくなる、下階に騒音が伝わらなくなるなどです。問題としては、床下に排水の勾配がとれないということがあります。そのため配管の上に床を張りますけれども、そこが非常に厳しい条件になってきます。一方、スラブ下配管にはいろいろな問題がありましたが、唯一よかったのは、いくらでも排水勾配がとれたので、排水にとっては天井裏配管というのはそんなに悪いことではなかったんです。
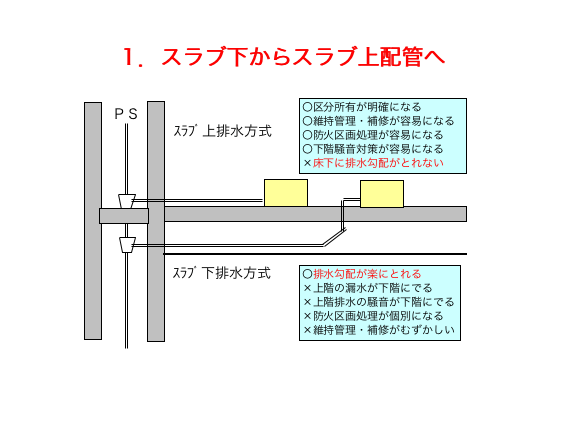 |
| ▲fig.1-01 |
先日、霞ヶ関ビルを設計された池田武邦先生にお話をうかがったときに、先生は海軍にいらっしゃったので造船業に非常に明るくて、船をつくるときはほとんど工場でつくったものを現場で組み立てるだけなのだそうですが、そういうものをこの霞ヶ関にも入れたとおっしゃっていました。ご承知のように、霞ヶ関ビルのトイレは壁つきのユニット化をしています。あれはアメリカ式の方法で、壁に荷重をまかせるための仕掛けをもっています。その後昭和47年くらいから住宅における設備のユニット化がいろいろな形で進んできました。昭和47年に設立された(社)日本住宅設備システム協会は本来バスユニットを普及させるためにつくられた協会でしたが、ここでももう少し広い範囲のシステムをやろうということになりました。ユニット化できるということは、要するに、床上で処理するという考え方を支援しているわけです。直床でいろいろな防水処理をするのは非常に難しい。穴をあけるわけにもいかず、床上で転がしていくために二重の床をつくった防水方式ができてくる。しかしそういう床上配管を支援するユニット化の方法が出てきたために、配管システムが床上に上がってきたと言えるのではないかと思います。
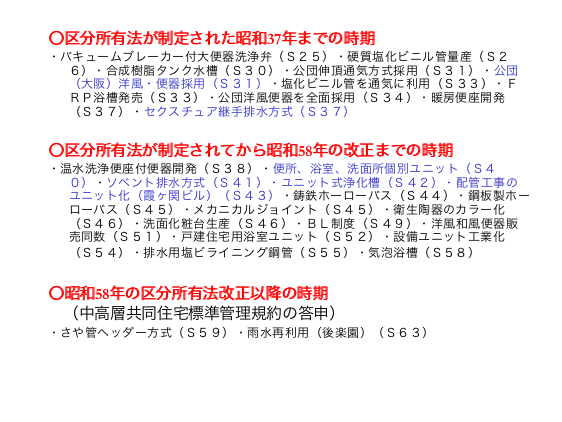 |
| ▲fig.1-02 |
2番目のテーマは「二管式から単管式へ」です[fig.1-03]。基本的に排水の立て管は、従来は二管式、すなわち排水管と通気管があって、片方は水が流れてもう一方は空気が上に上がって外気へ逃げていく仕組みになっている。これはどちらかというとアメリカで使われてきた方式です。それに対して、1本の配管で上のほうに伸頂通気管をつける、いわゆる単管式と呼ばれるシステムは、どちらかというとヨーロッパで使われてきた方式です。この2つがどっと日本に入ってきて、さてこれからどういう方向で考えるかというときに、排水の継手の開発が進んできました。もともとこの継手は日本にはなかったため、スイスのソベント、もしくはフランスのセクスチャーという継手が導入されています。こういう継手が入ってくることによって単管式が出てきたわけですけれども、問題はヨーロッパでは8階建てくらいの建物で使っているのに対して、日本は8階にとどまらずに次第に高層化が進んでくる。ここから特殊排水継手のいろいろな開発テーマが出てきたわけです。
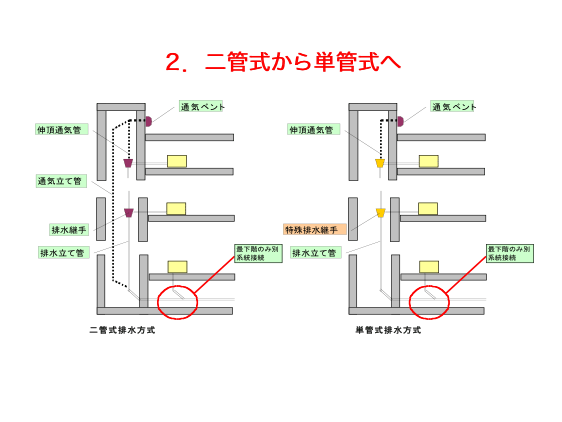 |
| ▲fig.1-03 |
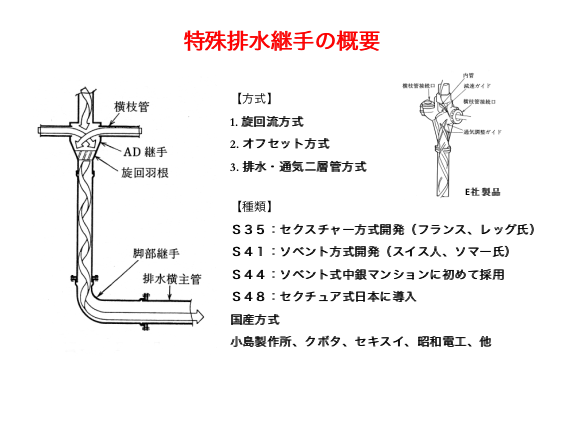 |
| ▲fig.1-04 |
特殊排水継手の性能は重要です。例えば11階建の建物の10階から排水を流すと、配管を流れていくときに上の空気をどんどん吸い込んでいく。そうすると配管のなかは負圧になります。管内圧力には正圧と負圧がありますが、次第に下にいくにしたがって負圧は終わり、1階へ近づくと配管は脚部で曲がるため、今度は逆に正圧になります。上から水が落ちてくると、上の空気は引っ張られるし、下の空気は押し込まれるような形になるからです。そうした配管のなかの空気の圧力の変化はfig.1-05のようになります。これは管内の圧力を表示していますけれども、これがある一定の圧力を超えると、継手に接続されている横枝管の各種衛生器具のトラップの封水に影響を与えます。その封水の深さが一般に50mmと言われるのは、50mmAq(0.4903kPa)の圧力に耐えられるということですので、管内の圧力変動が50mmAq以内であれば、その封水は飛ばないということです。ですから、どれほど配管のなかの圧力変動の幅を小さくできるかというのが特殊排水継手の能力表示です。配管のなかの圧力変動が小さければ小さいほど流量はたくさん流せるということなので、排水継手の開発競争は、どれだけの水を流せるかを表わす「許容流量」の競争になったわけです。その結果いろいろな工夫がなされた継手がつくられました。流量が増えて圧力の変異の幅が膨らんで400パスカルを超えると、破封が起きます。逆にマイナスになると吸引されてしまいますから、立て管には一定の流量しか流せないことになります。このような排水能力曲線を各社が提示するようになっています。
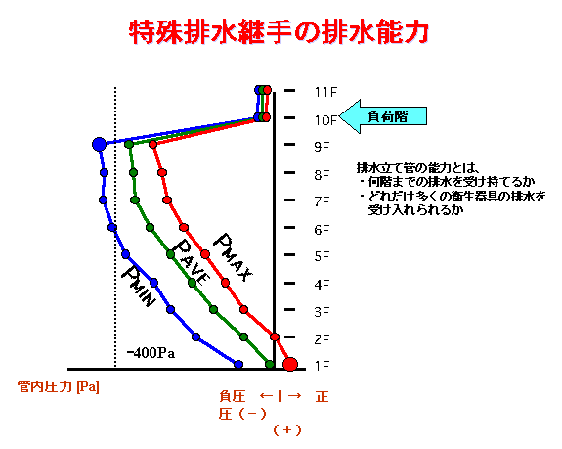 |
| ▲fig.1-05 |
ヨーロッパでは8階建てまでが単管式の領域だったのですが、日本に入ってきて初めて30階建て以上の建物に単管式排水システムを入れることができるようになったと言えます。

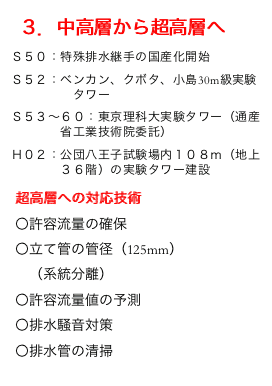
| ▲fig.1-06 |